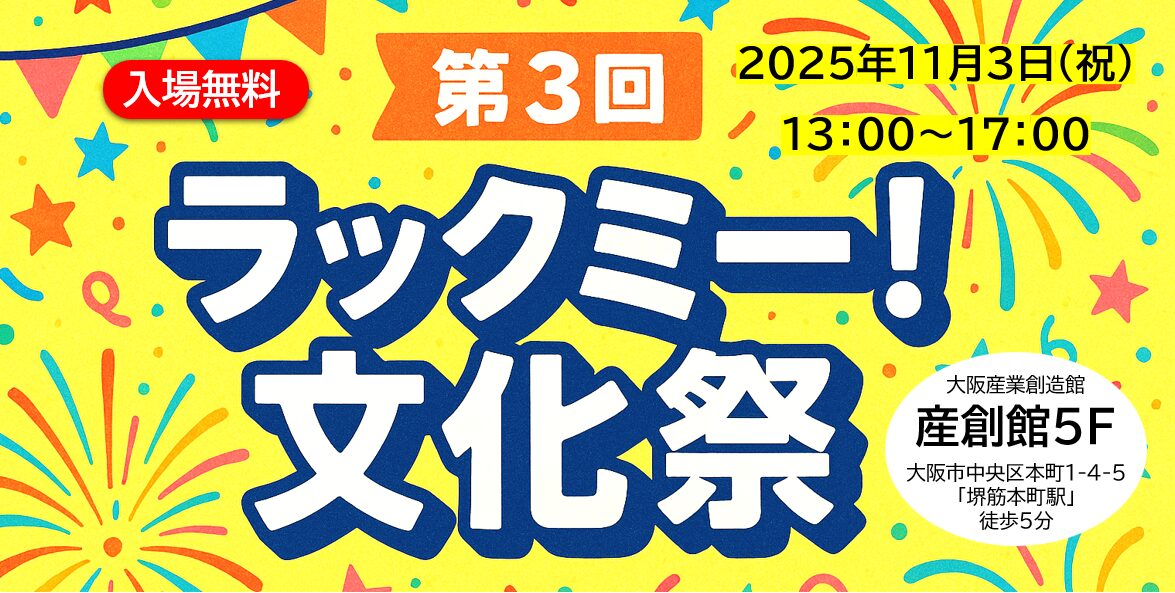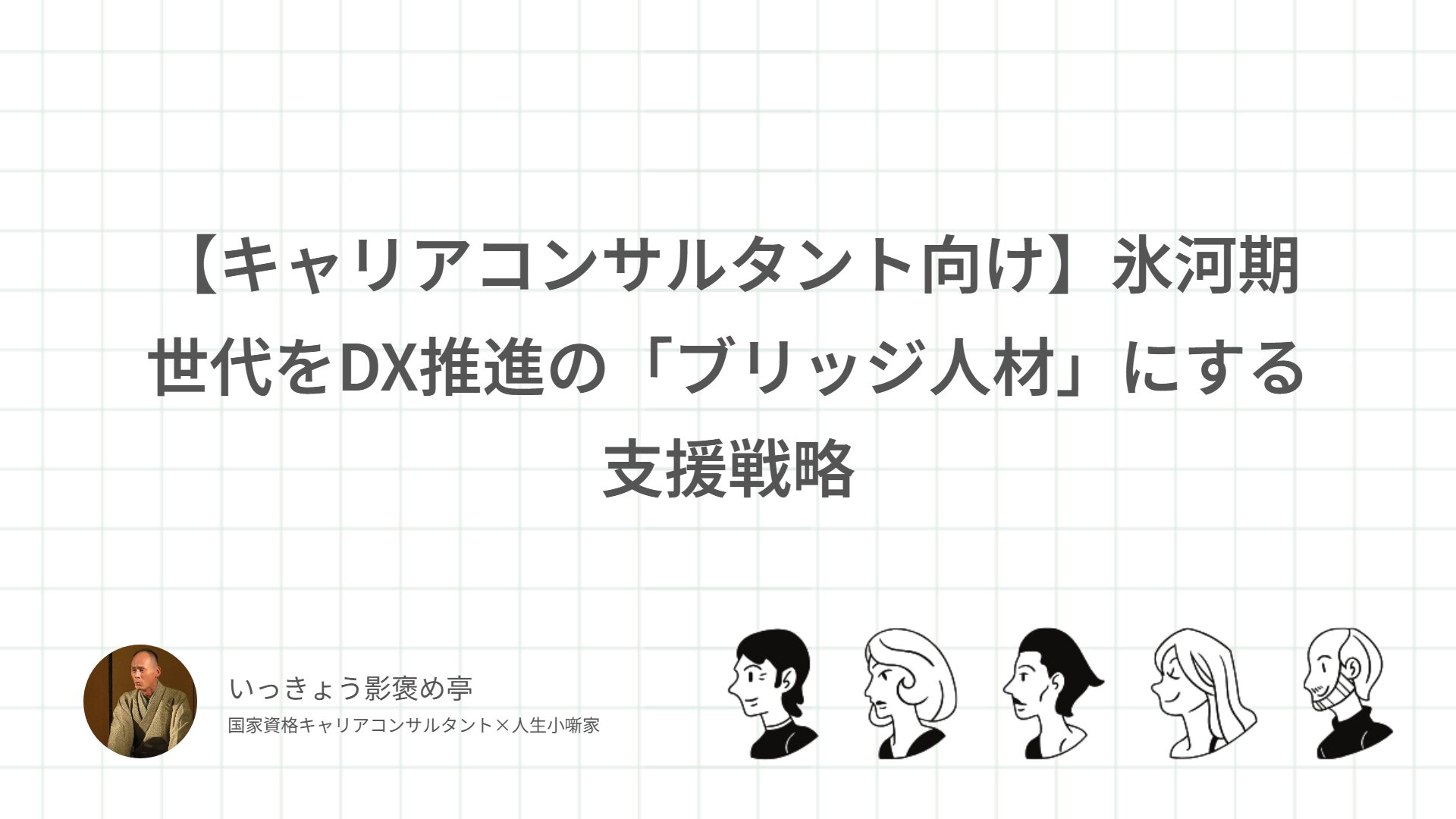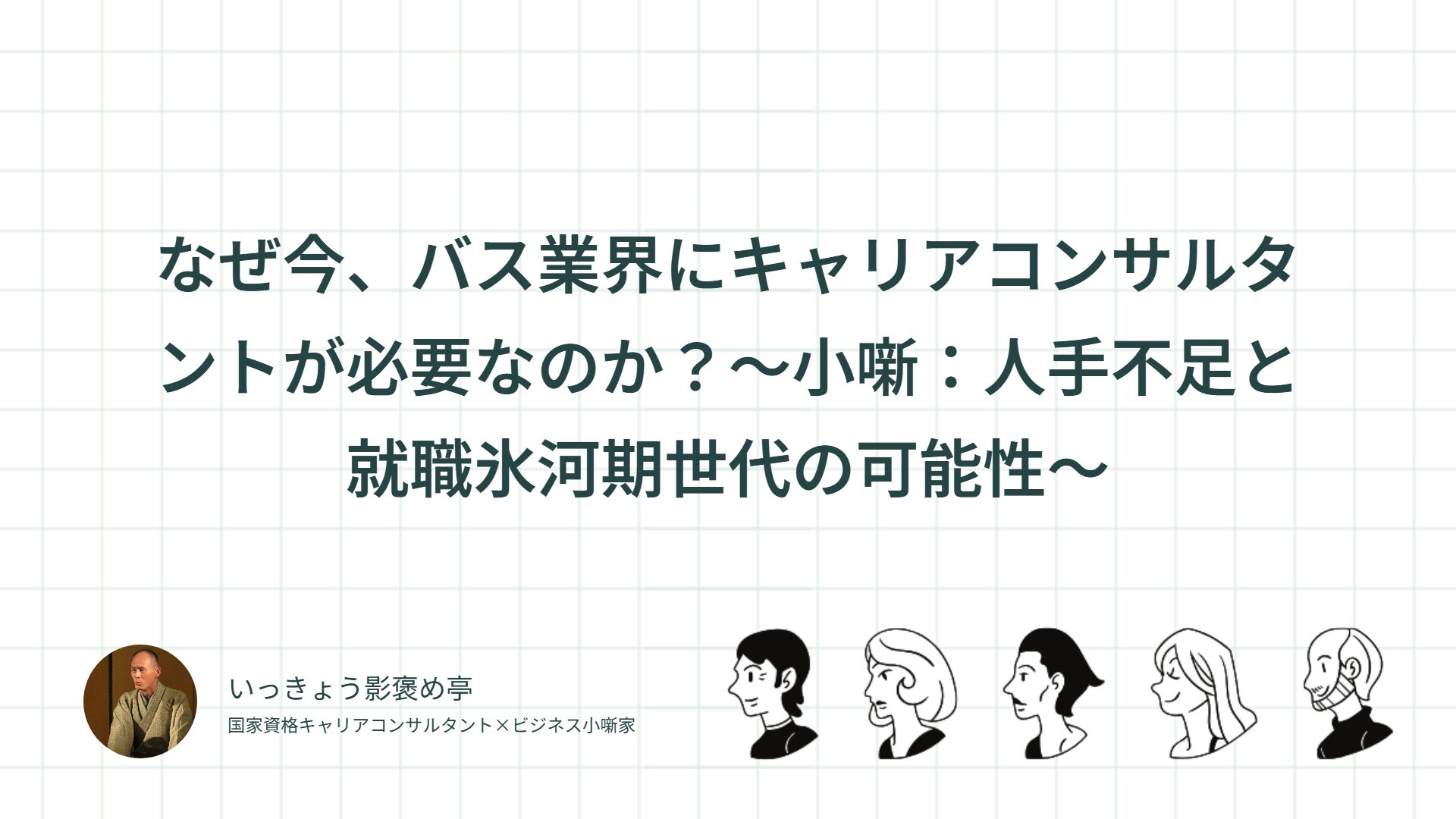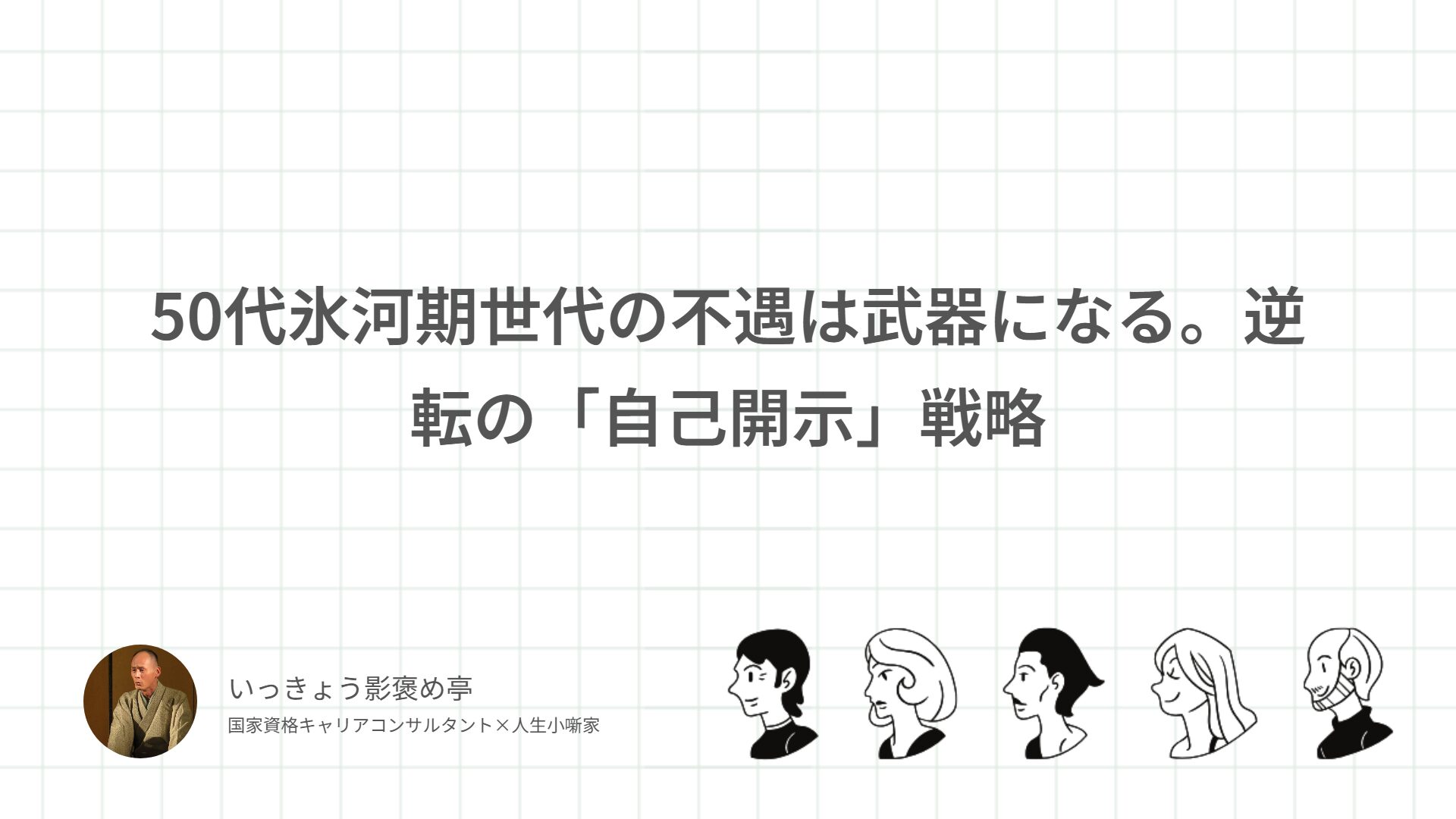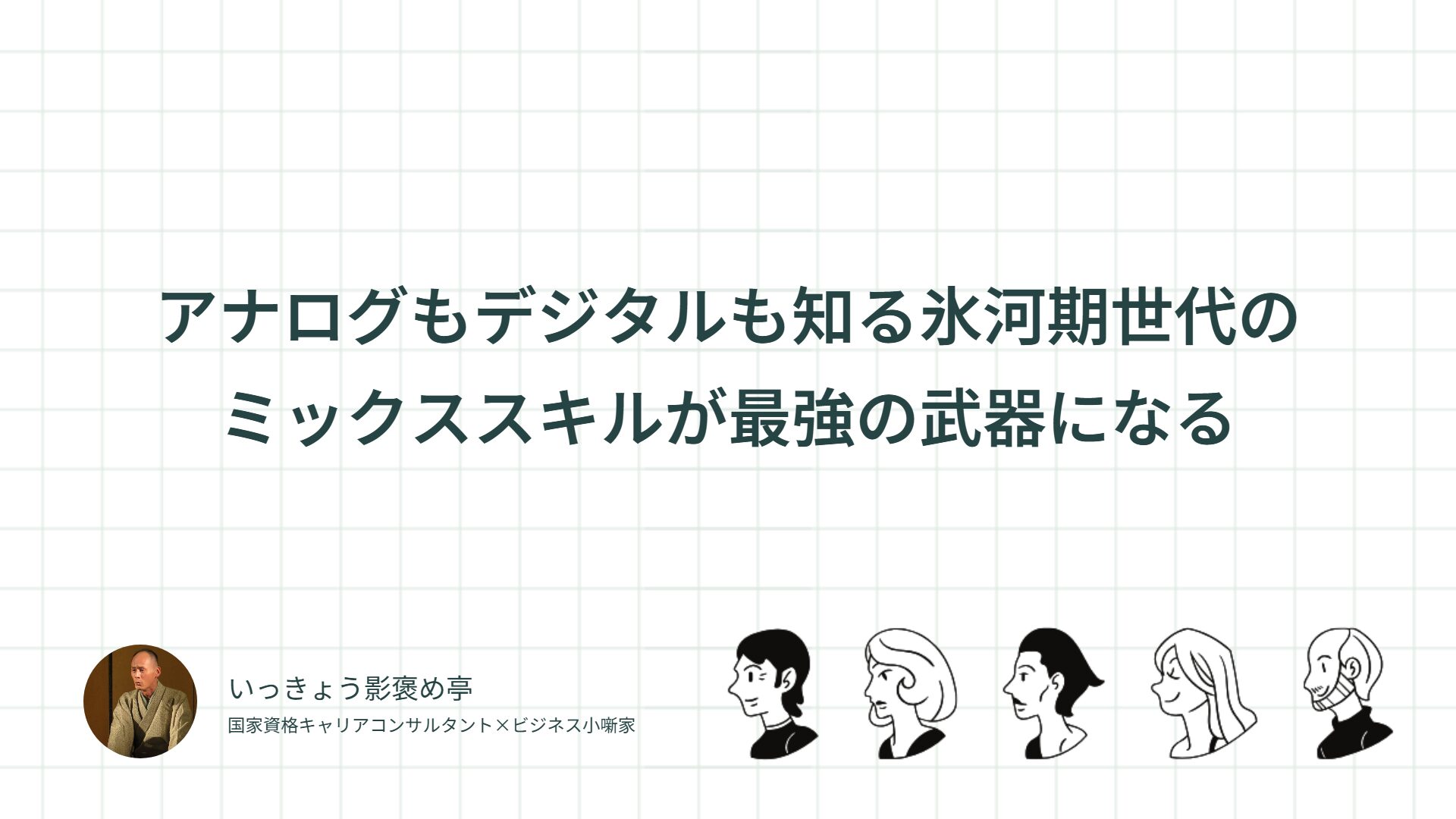なぜ「落語」が、あなたのキャリア支援スキルを最高レベルに引き上げるのか?
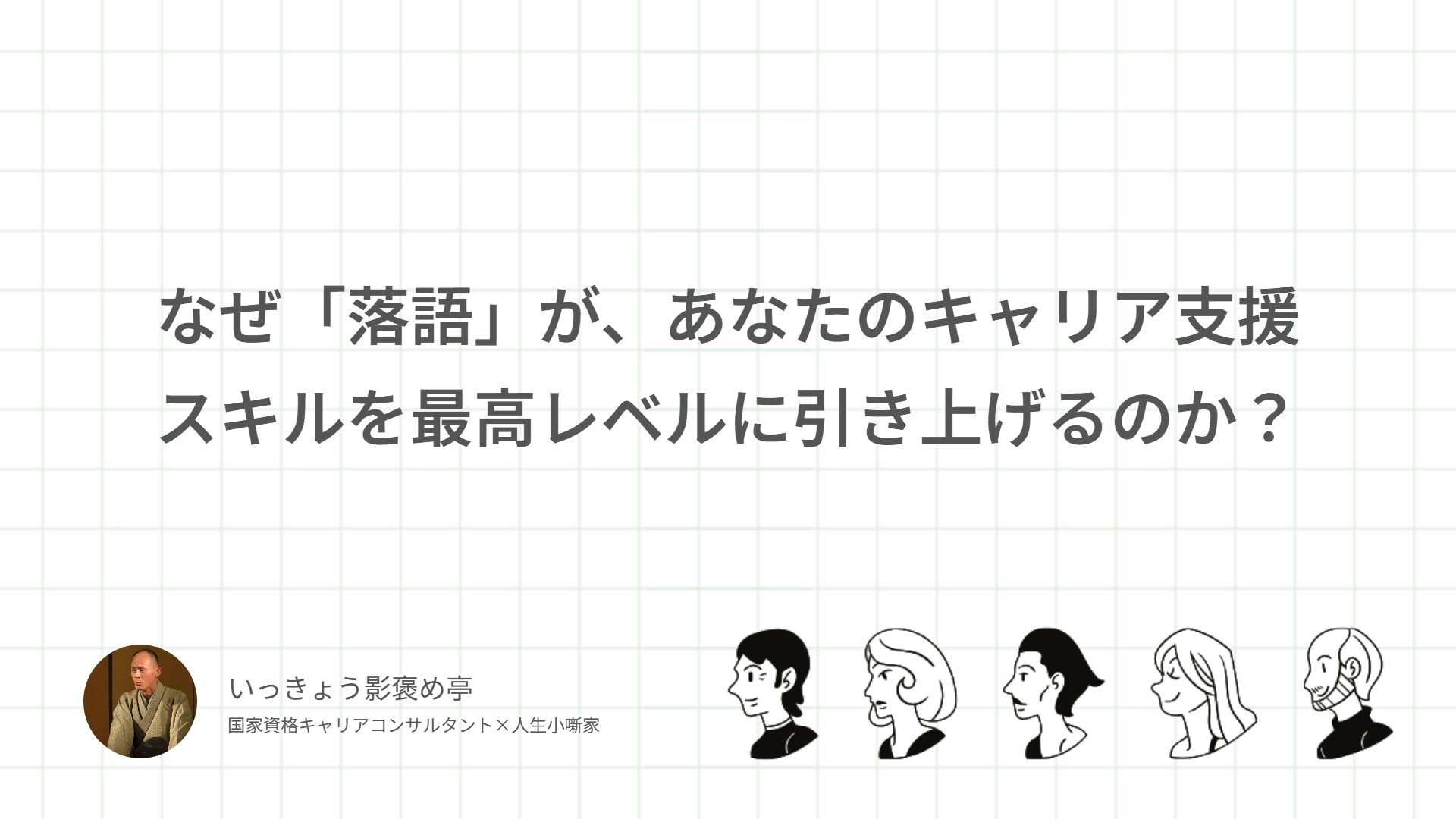
【マクラ】
私たちキャリアコンサルタントは、日々クライアントとの「対話」に向き合っています。
しかし、クライアントの「聴く態勢」をいかに作るか 1、そして、時には耳の痛いフィードバックをいかに「内省」 2 につなげてもらうか、常に悩むところです。
この度、私はLinkedInで「落語×キャリア戦略」というテーマで、ビジネスパーソン向けの発信(ニュースレター)を始めることにしました。
「なぜ、今さら落語?」
そう思われるかもしれません。
しかし、14年間落語を実践してきた私がプロのキャリアコンサルタントの視点で分析した結果、落語とは「究極のカウンセリング技術の体系」である、という結論に達しました。
ビジネスパーソンには「キャリア戦略の指南書」として提示する内容を、このブログでは、「私たちの支援技術(スキル)の指南書」として再編集し、解き明かしていきます。
落語の「起源」は「カウンセリング」である
「落語」と聞くと、エンターテイメントを想像するかもしれません。しかし、その起源はまったく別の場所にありました。
落語のルーツは、安土桃山時代の僧侶・安楽庵策伝が、大名(クライアント)に向けて語った「説法(カウンセリング)」であったと言われています。
当時の僧侶は、現代のカウンセラーやコンサルタントのような役割も担っていました。
しかし、耳の痛い真実や難しい教えをそのまま伝えても、位の高い大名たちはまともに聴いてくれません。
そこで彼らが生み出した技術が「落語」です。
「苦い話しを笑いというオブラートに包んで内服させる」
相手が自ら「あ、そうか」と気づきを得られるように設計された、高度なコミュニケーション技術こそが落語の本質なのです。
これは、クライアントが自ら内省し、気づきを得るプロセス(自己理解)を支援する、私たちキャリアコンサルタントの仕事と全く同じ構造を持っています。

なぜ落語は「伝わる」のか? 〜すべては「聴く態勢」のために〜
クライアントの価値観を引き出す上で、相手に「伝わって」始めて支援は意味を持ちます。落語は、その「伝え方」の技術の宝庫です。
落語の世界では「落語は聴き手の芸」と言われます。
演者がどれほど優れていても、聴き手に「聴く態勢」がなければ、その芸は成立しません。事実、落語の成否は「場づくりが8割」とも言われ、聴く気がなければ構成もテクニックも役に立たないのです。
- 寄席の金屏風やめくり、見台といった舞台装置は、聴き手の集中力を高めるための「仕掛け」です。
- 物語の「型(序破急)」は、聴き手が迷わず物語に没入し、自ら情景を「補完」するための設計図なのです。
これは、私たちの支援現場でも同じです。
クライアントの「聴く態勢(=安心して話せる場)」を作れなければ、どんなに優れた問いも機能しません。落語は、そのための「場づくり」と「型」のすべてが詰まっているのです。

支援技術の核=落語の核=「間(ま)」の力
では、落語の「伝える技術」とは具体的に何でしょうか。
「息の使い方」「仕草」「目線」など、様々な技術がありますが、その全てを支配するのが「間(ま)」の力です。
「間」は、単なる「沈黙」ではありません。
それは「一番言いたいことのために間を戦略的に使う」、最強の技術です。
「間」は、聴き手に「考える時間」を与え、聴き手の「補完力」を最大化させます。そして、演者(支援者)と聴き手(クライアント)の間に強固な「信頼」を生み出す装置となります。
この「間」を使いこなす力は、私たちが最も重視する「傾聴の技術」であり、相手が自らの物語を見つめ直す「ナラティブ・セラピーの極み」にほかなりません。
これこそが、私たちの「支援の質」を高める核となる武器なのです。
【結び】あなたの「支援現場」にどう活かすか
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
LinkedInでは、この内容を「ビジネスパーソンのキャリア戦略」という切り口で発信していきます。
しかし、このブログの読者である「支援者の皆様」には、ぜひこの「落語の型」を、クライアントの「自己理解を促す技術」や「信頼関係を築く技術」として読み解いていただけたら幸いです。
落語の「人情噺」が、登場人物の物語を見つめる聴き手自身を癒すように、私たちの支援もまた、「間」の力を通じてクライアントの内省を深めることができます。
最後に、支援者の皆さんにお聞きします。
あなたは、ご自身の「支援現場(カウンセリング)」で、クライアントの内省を促すために、あえて「間」を戦略的に使った経験はありますか?
追伸:「落語×キャリア」の“楽屋裏”へようこそ
今回の創刊号(ブログ版)をお読みいただき、ありがとうございます。
このブログやLinkedInニュースレターでは、キャリアコンサルタントの視点から「落語の思想(Why)」を“表舞台”の言葉として、今後も発信していきます。
ですが、すでにお届けしているEメールマガジン(メルマガ)では、さらに一歩踏み込み、「メルマガでしか読めない」限定コンテンツをお届けしています。
もし、あなたが「思想」だけでなく、その「実践的な裏側」まで深く知りたいと思っていただけたなら、ぜひメルマガの“楽屋”にも遊びに来てください。
【メルマガ限定コンテンツの例】
- ブログでは書けない「実践の裏側(How)」
- (例:今回の『間』の力を、実際のカウンセリング()現場でどう使っているのか? その具体的な失敗談と改善策は?)
- 最新の「試行錯誤」のプロセス(思考の生ログ)
- (例:新しい落語ネタ(キャリア論)をどう組み立てているか、その生々しい思考のプロセスを共有)
- 読者限定の「公開壁打ち」や「Q&A」
- (例:「こういうクライアントがいて…」といったご相談に、落語の型()を使って回答する企画)
“表舞台”の思想(ブログ)と、“楽屋裏”の実践(メルマガ)。 両方をお楽しみいただけると、より深く「落語×キャリア戦略」の神髄に触れていただけるはずです。
ご登録を心よりお待ちしております。
▼メルマガ登録はこちらから