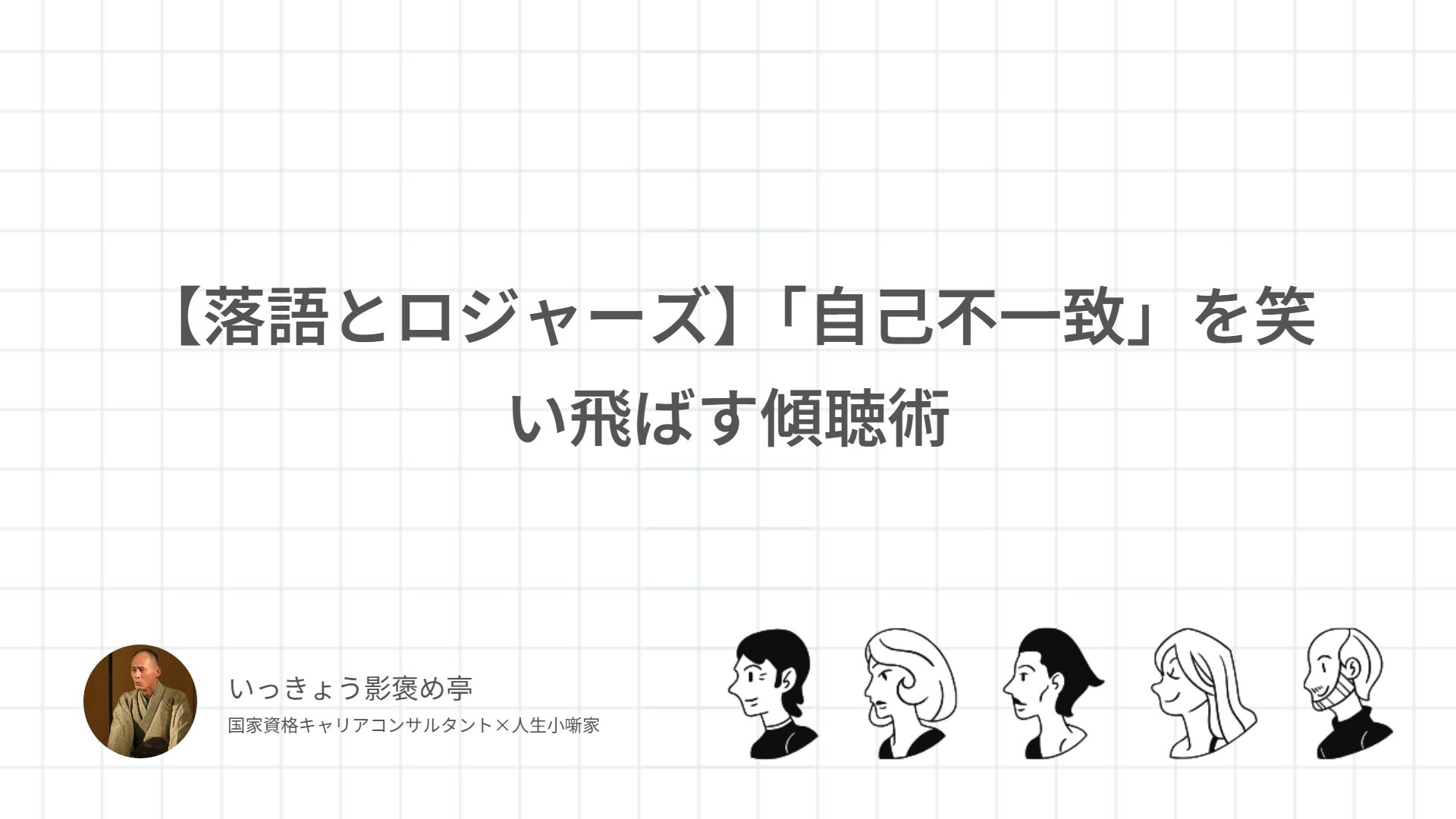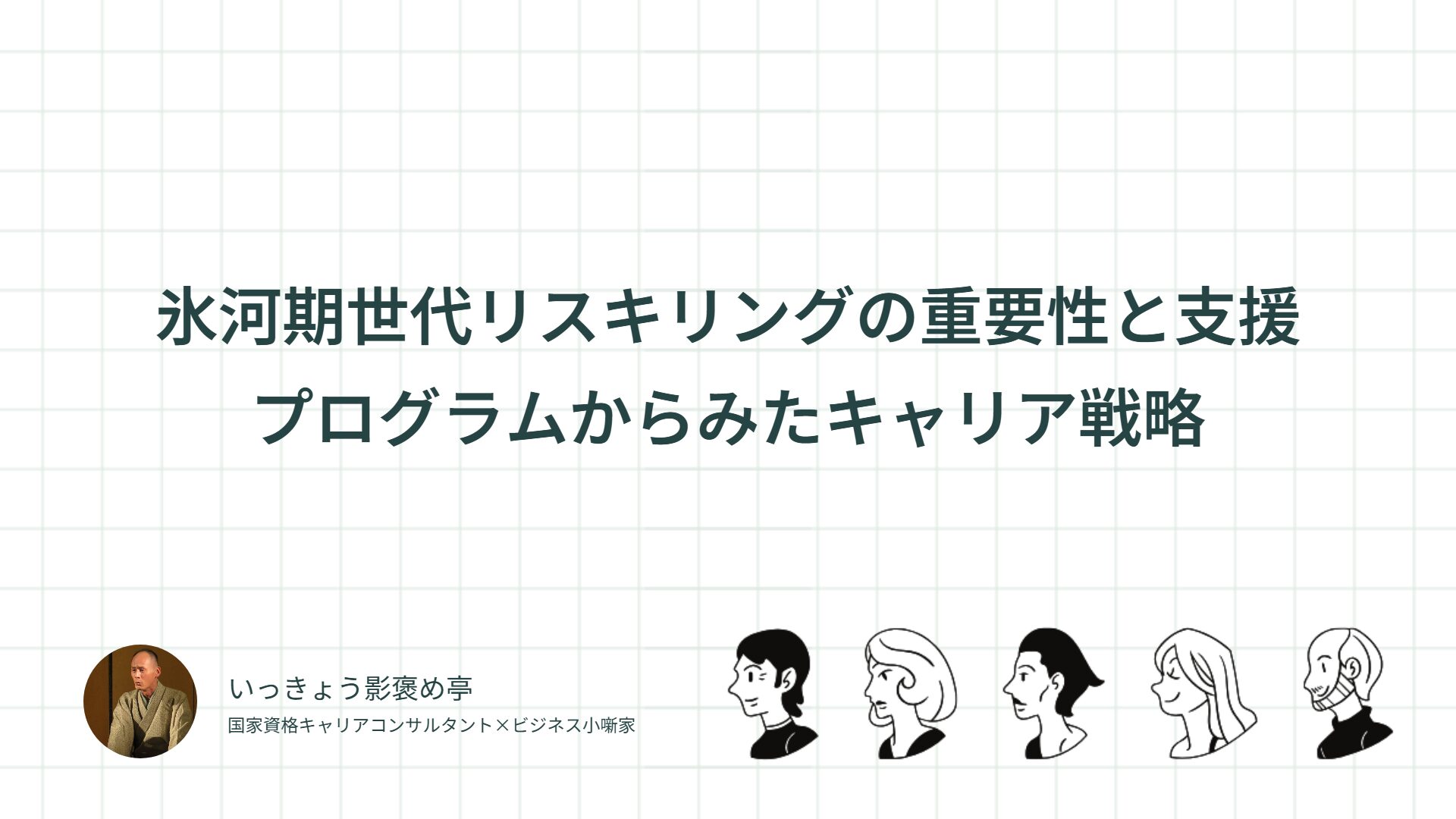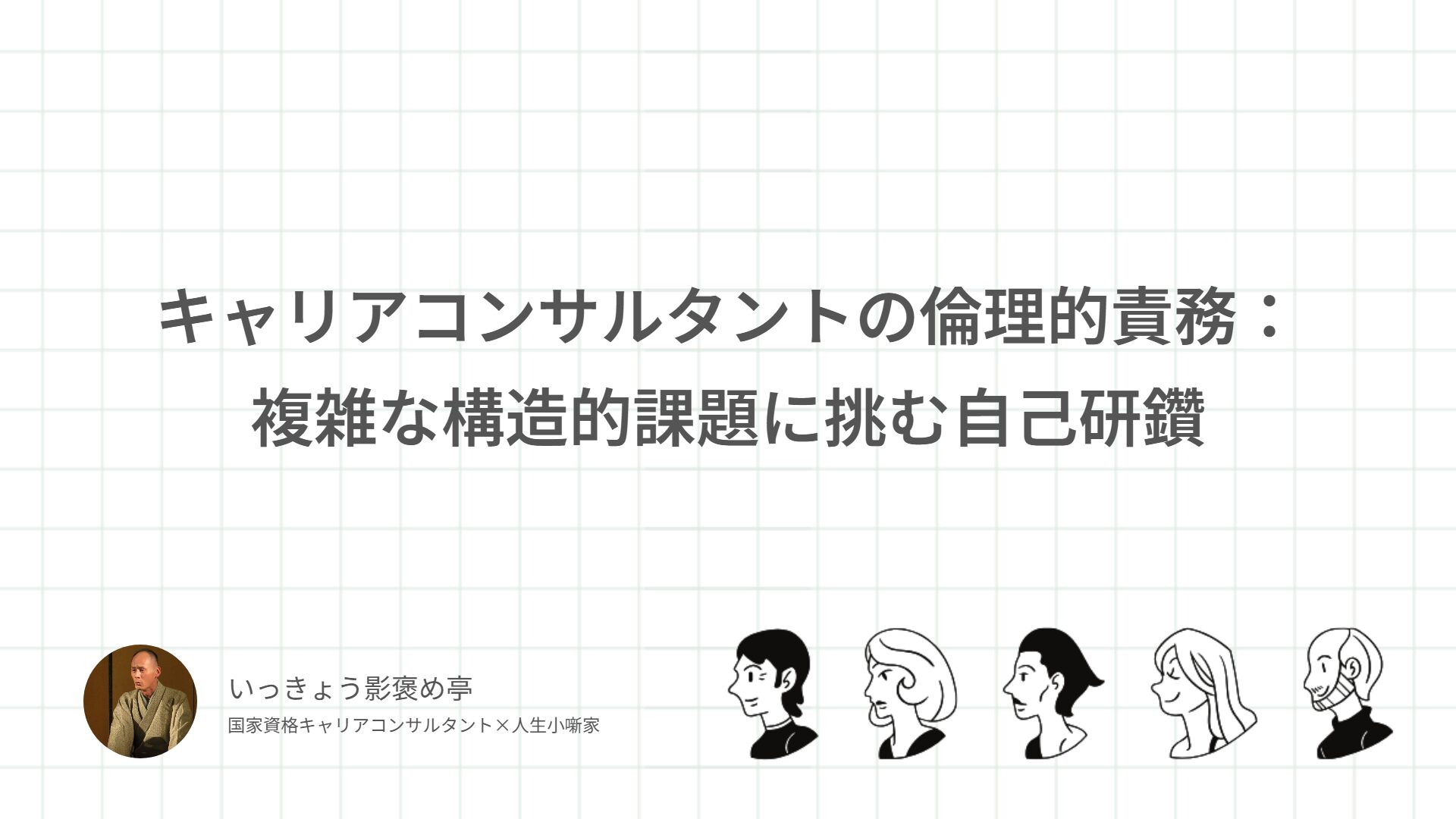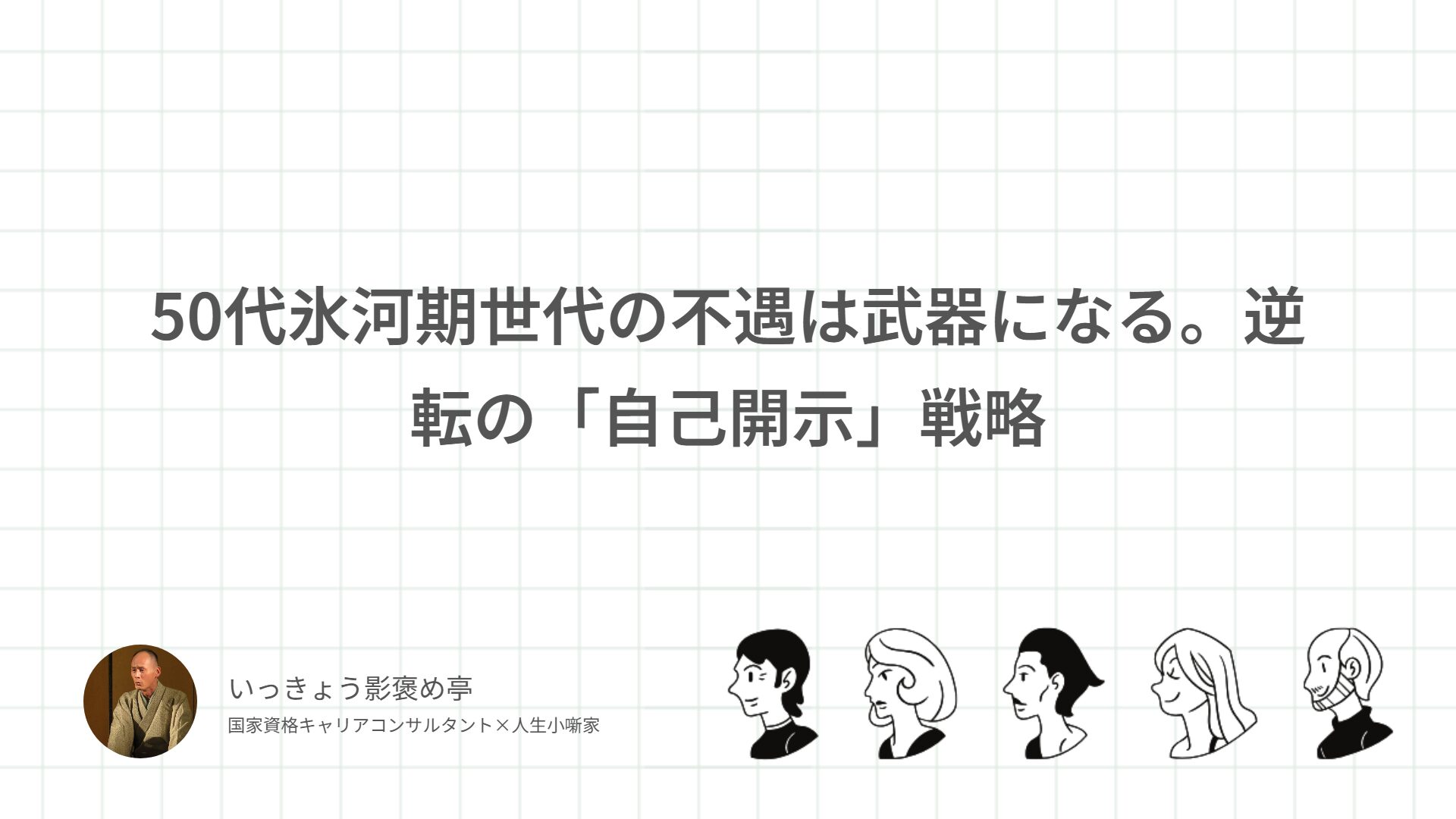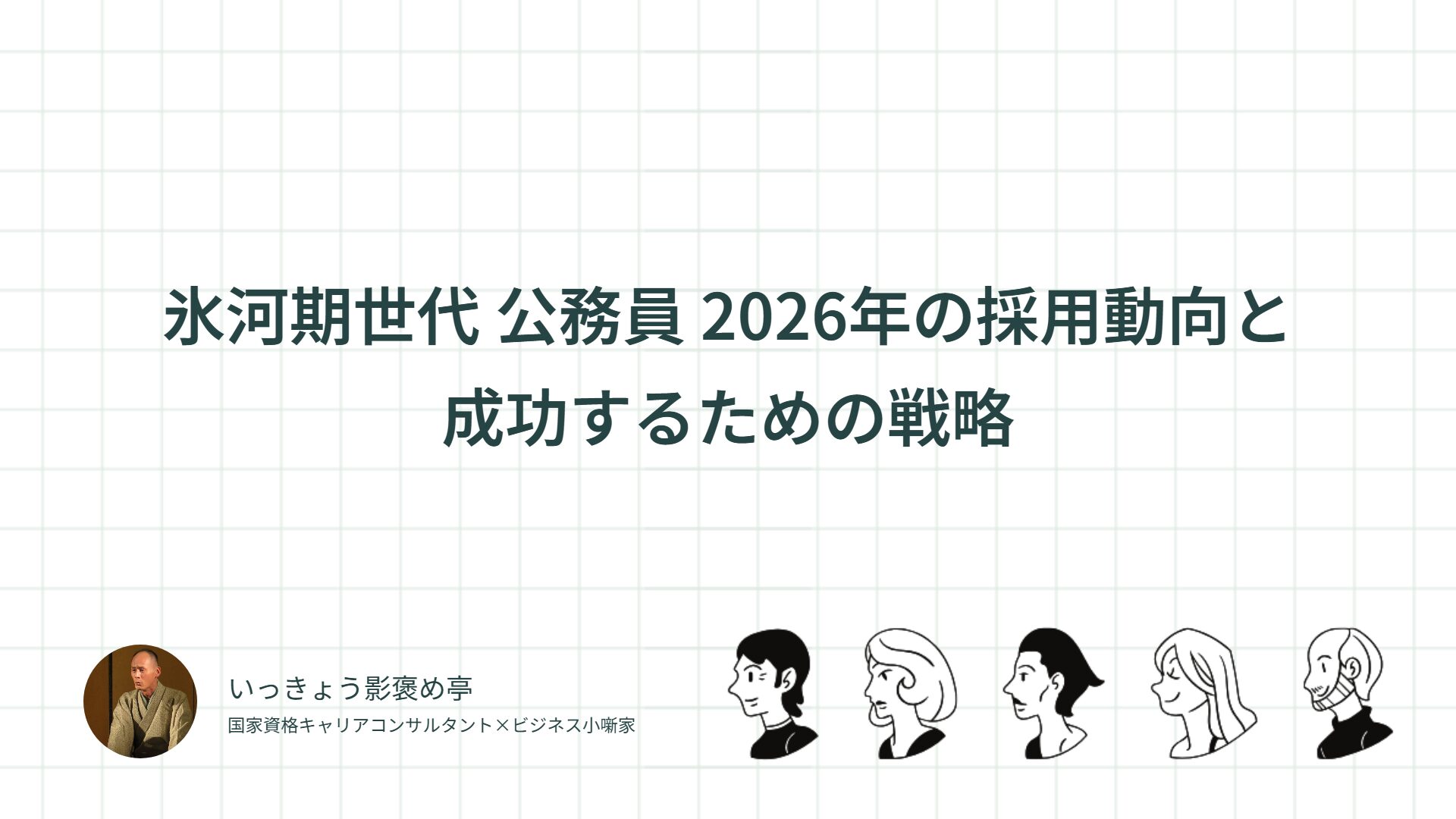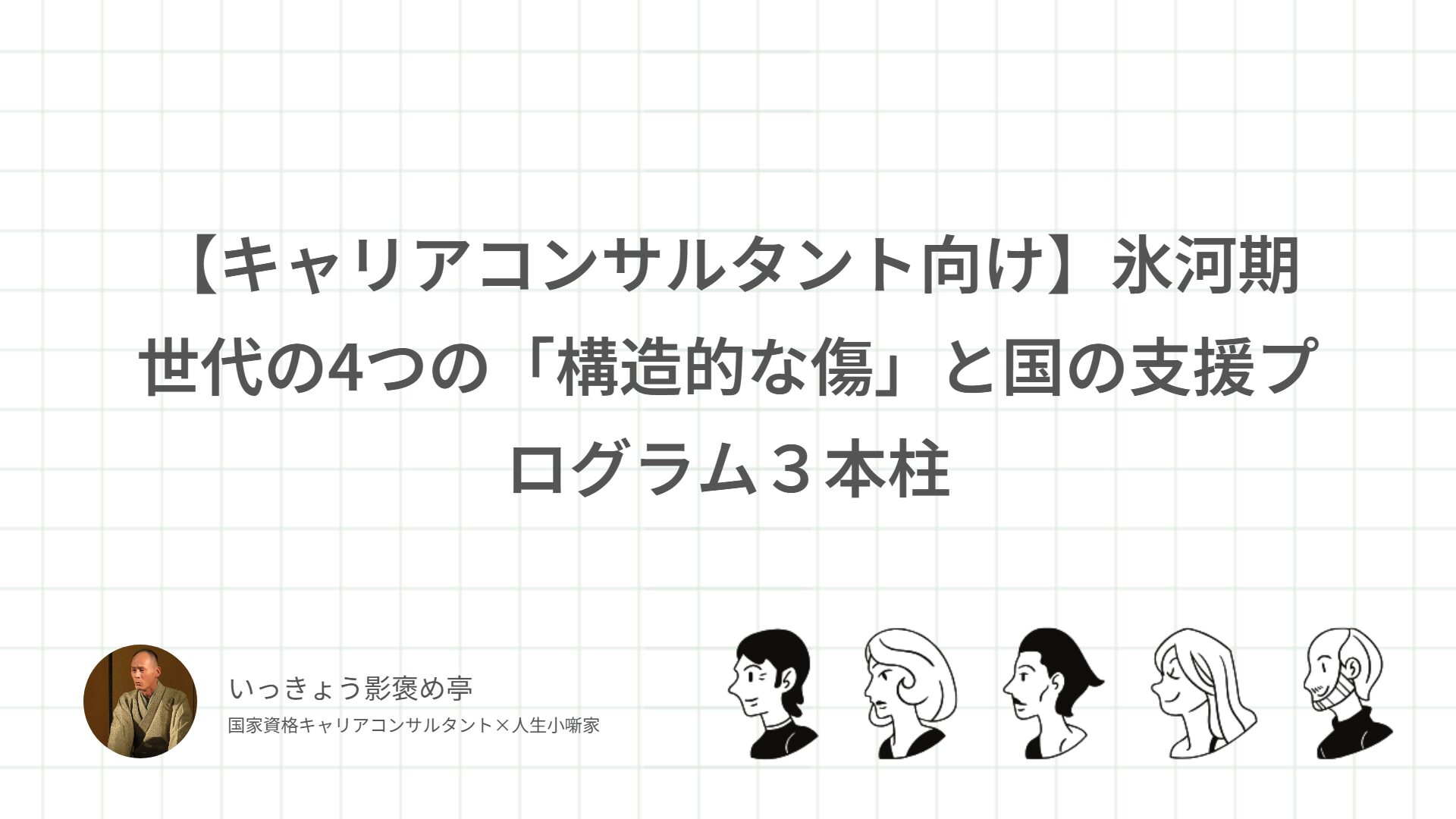【キャリアコンサルタント向け】老後貧困を回避せよ!不本意非正規組へのホリスティック支援戦略
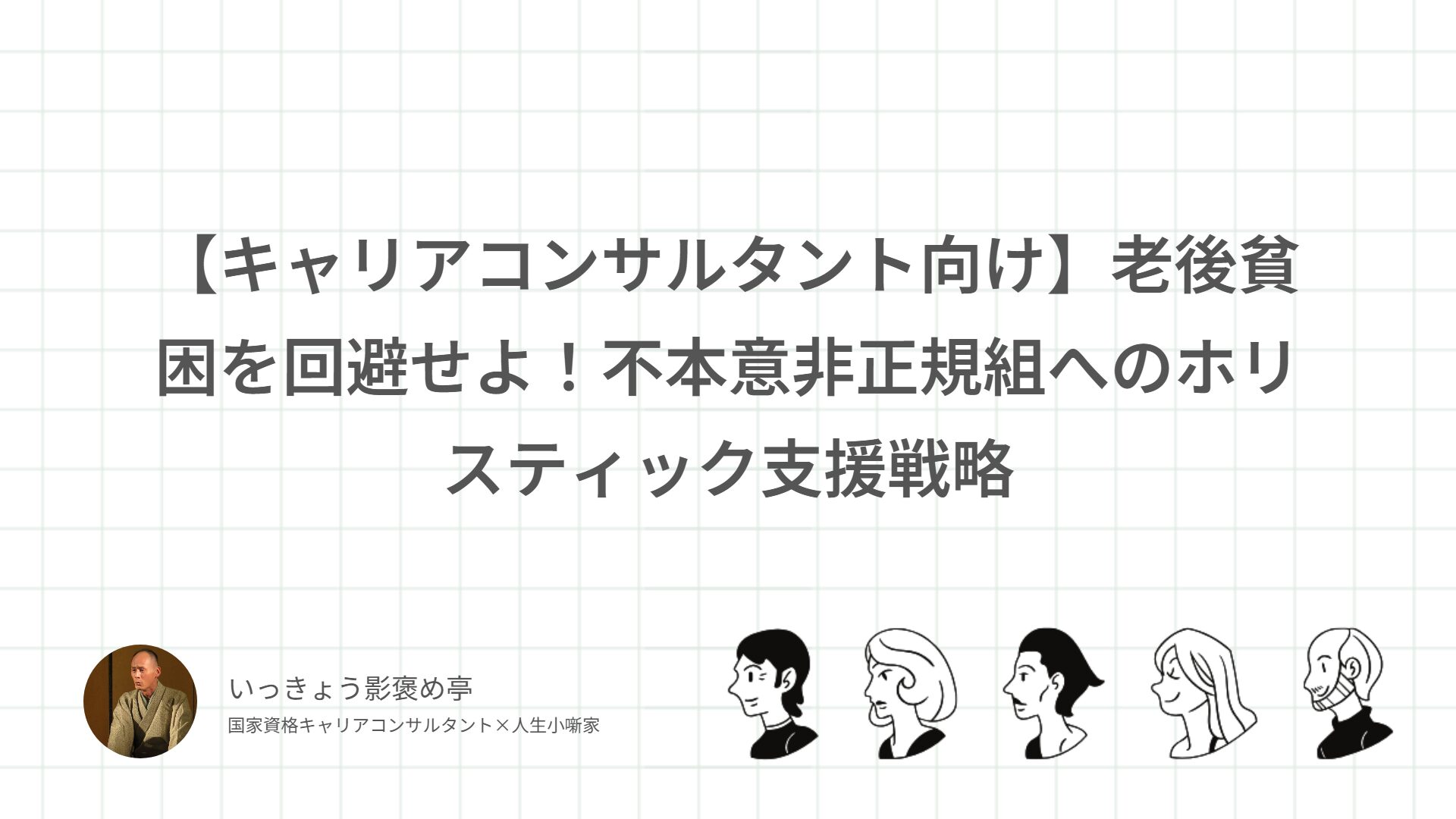
キャリアコンサルタントの皆様。
このグループにとって「安定」とは、正規組のように守るべきものではなく、キャリアの出発点から奪われ、今なお切望し続けている目標そのものです。特に就職氷河期世代には、正規雇用を望みながら非正規で働く「不本意非正規雇用者」が依然として多く存在します。
本記事では、彼らが直面する長期的な傷跡と将来の社会保障危機を診断し、生活基盤、心理、スキル再構築を統合した多角的(ホリスティック)な支援戦略と実践ステップを解説します。
奪われた「安定」と長期的な困難の構造
このグループが抱える課題は、個人の能力不足ではなく、バブル崩壊後の「構造的なショック」がもたらした長期的な傷跡です。
1-1. 構造的ショックがもたらした長期的な傷跡
- 不本意非正規の固定化: 2024年時点でも、正規雇用を望みながら非正規で働く「不本意非正規雇用者」が、就職氷河期世代の中に約35万人存在します(出典:総務省統計局「労働力調査(詳細集計)」より)。
- 埋めがたい賃金・資産格差: キャリアの途中で正社員になれたとしても、新卒正社員の同世代と比較して、平均年収が男性で約130万円、女性で約180万円も低いという長期的な賃金格差が残っています。
(賃金格差の論拠:厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」を基にした分析より。特に、40代・50代の正規組と新卒で正規になれた同世代を比較した場合、賃金上昇率に大きな差が生じ、生涯賃金に影響を及ぼしています。日本人材ニュースの分析をご参照ください)。
1-2. 将来の社会保障危機と老後不安
- 老後貧困リスクの高さ: 厚生年金への加入期間の短さや低賃金のため、将来受け取る年金額が著しく低くなり、特に単身女性は「老後貧困」に陥るリスクが極めて高いと指摘されています。クライアントの心底にある「このままでは人生終了だ」「結局、自分は社会に見捨てられた」という希望を失いかねないほどの絶望感に、支援の最初期で向き合う必要があります。
- 社会的孤立と8050問題: 経済的な困窮は社会からの孤立を招きやすく、「8050問題」の当事者となるリスクも高まっています。「誰にも相談できない」という孤立感は、キャリア再構築の最大の壁となります。

キャリアコンサルタントに求められる支援戦略:「ホリスティックな安定の獲得」
このグループへの支援は、生活基盤、心理的サポート、スキルの再構築を組み合わせた多角的かつ統合的な支援でなければ成功しません。
- ホリスティックとは?: 複合的な課題を持つクライアントに対し、単一の問題解決に留まらず、生活基盤、心理、社会参加、経済など全ての側面から支援を統合することを意味します。これは、国際的な職業能力開発プログラムの知見を応用した、現代のキャリア支援に不可欠な視点です。
(出典:厚生労働省「地域共生社会の実現に向けた取組」資料など)
2-1. 潜在能力の「翻訳」と自信の回復
キャリアコンサルタントは、クライアントの持つ独自の強みを掘り起こし、言語化すべきです。複数の業界や職種を渡り歩いた経験を、企業が求める「DX時代のブリッジ世代」としてのハイブリッドなスキルとして捉え直すことで、クライアントの自己肯定感の回復を促します。
2-2. 質の高い雇用への移行と政策の活用
- 生活保障付きの学び直し: 経済基盤が脆弱なクライアントには、生活支援給付金(月10万円)を受給しながら無料の職業訓練を受けられる「求職者支援制度」の活用を積極的に支援すべきです。
(出典:厚生労働省「求職者支援制度のご案内」) - 英国YTSの罠を回避: 国際的な教訓が示す通り、訓練プログラムが安価な使い捨て労働力の供給源(雇用の置き換え)に終わることを避け、安定雇用への出口を厳しく見極める必要があります。


「社員」機会を発掘し、クライアントに安定を提示する
不本意非正規組において、「社員」になれることは、彼らが切望する「安定」に直結する重要なキーワードです。しかし、非正規の経験しかない方にとって、社員になるというイメージは湧きづらいものです。
私が所属しているバス業界では、乗務員募集を常に行っており、60歳からでも「社員」として働ける機会があります。このように、業界をつぶさにみれば、不本意非正規で苦労された方々にも機会は多くあるはずです。私たちキャリアコンサルタントの役割は、どの業界にどんな機会があるのかを知って、クライアントに伝えることであるといえます。
私は現在、バス業界を中心に、不本意非正規組の人口ボリュームゾーンが大きいことや、彼らが持つアナログとデジタルをハイブリッドに扱える特性を広める活動を、ブログやメルマガを通して発信しています。
アクションステップ:ホリスティック支援の実践手順
キャリアコンサルタントが不本意非正規組のクライアントに対し、ホリスティックな支援を実践するための具体的な手順です。
クライアントが抱える経済的な困窮度と社会からの孤立度を初期段階で診断し、支援の優先順位を「生活基盤の確保」に置くべきか、「職業訓練」に置くべきかを決定します。
「求職者支援制度」による生活保障を受けながら、DX関連など市場価値の高い分野での学び直しを並行して提案します。同時に、クライアントの多様な経験を「ブリッジ人材」としての価値に言語化し、自己肯定感の回復を促します。
従来の正社員登用だけでなく、クライアントの自律性を活かせる「社会起業」やフリーランスといった多様な働き方、そしてバス業界のように「50代、60代からでも社員として働ける」具体的な業界機会を提示し、挑戦を伴走支援します。
【結論】ホリスティック支援で「安定」を獲得する
キャリアコンサルタントの使命は、不本意非正規組のクライアントに対し、経済基盤、スキル、心理面の全てをカバーするホリスティックな支援を提供し、彼らが真に望む「安定」の獲得を伴走支援することです。

あなたの支援を「戦略的資産」へ進化させるために
このブログを読んで「さらに深く知りたい」と感じたキャリアコンサルタントの皆様へ。
著者いっきょうのメルマガでは、クライアント経験の「物語化」のコツや、深層心理の「読み解き方」など、現場で活かせる情報を砕けた内容でお届けしています。
あなたのコンサルティングを、より深く、より戦略的に進化させませんか?
➡️ 【無料メルマガ登録はこちら】