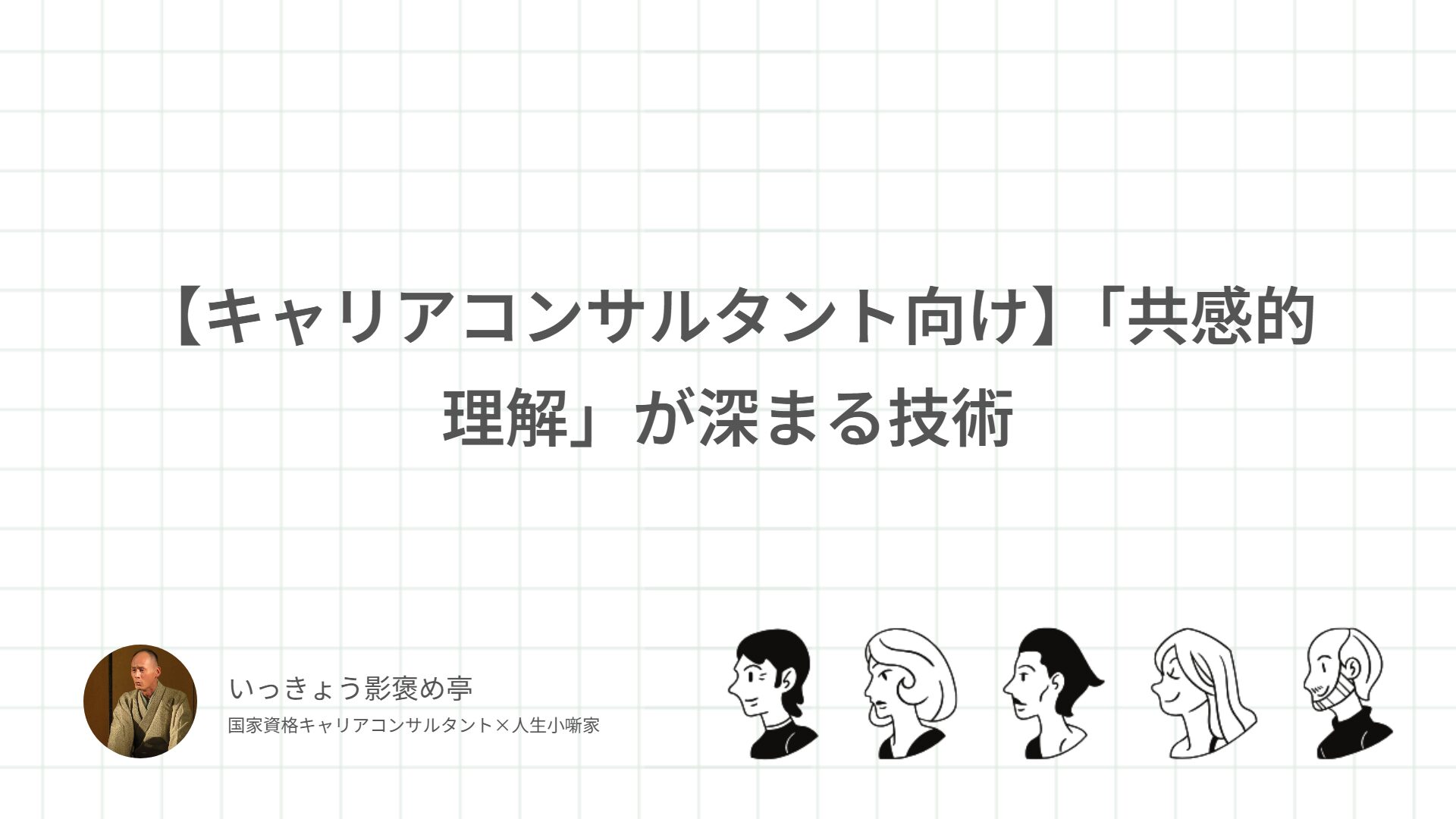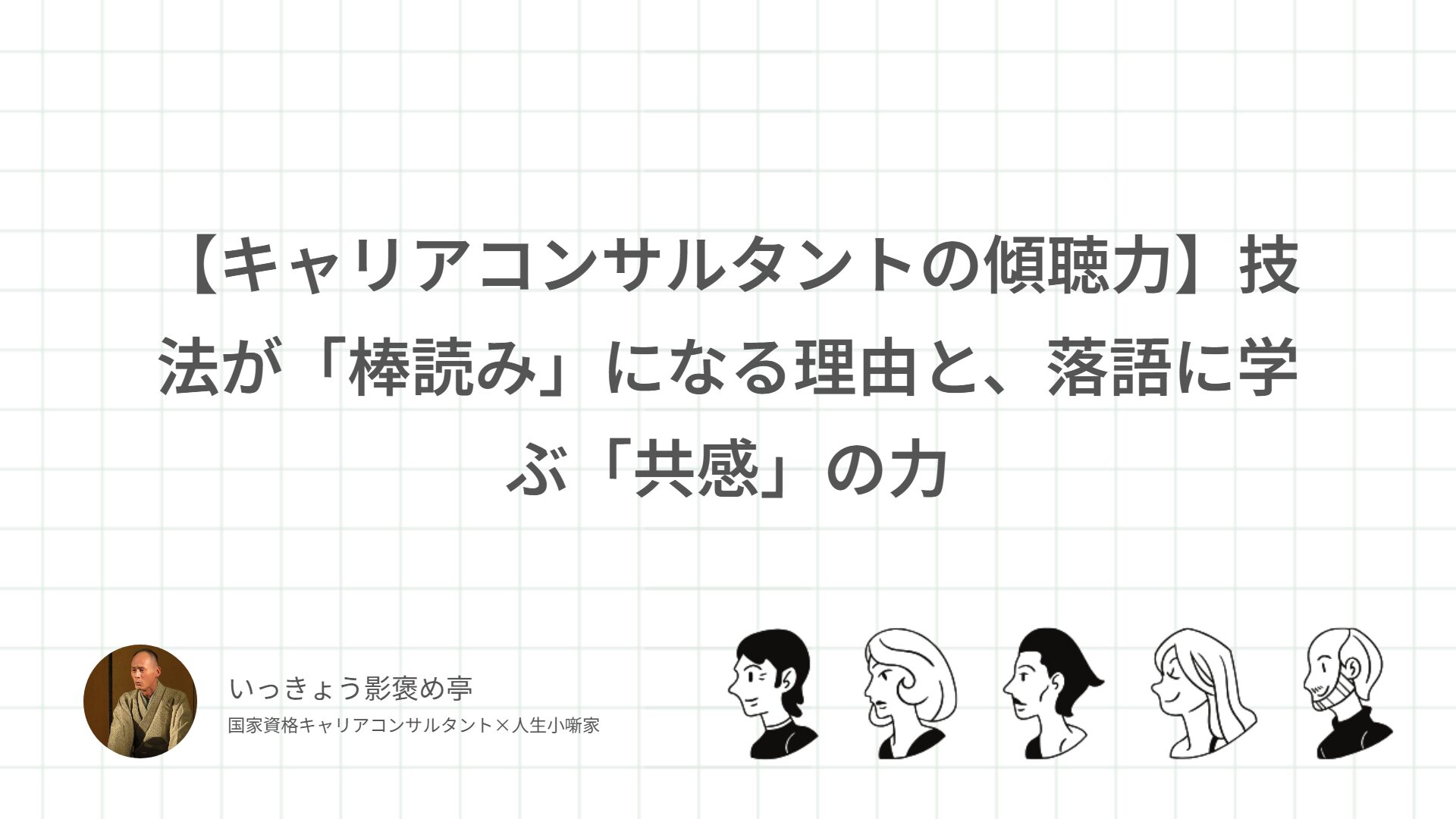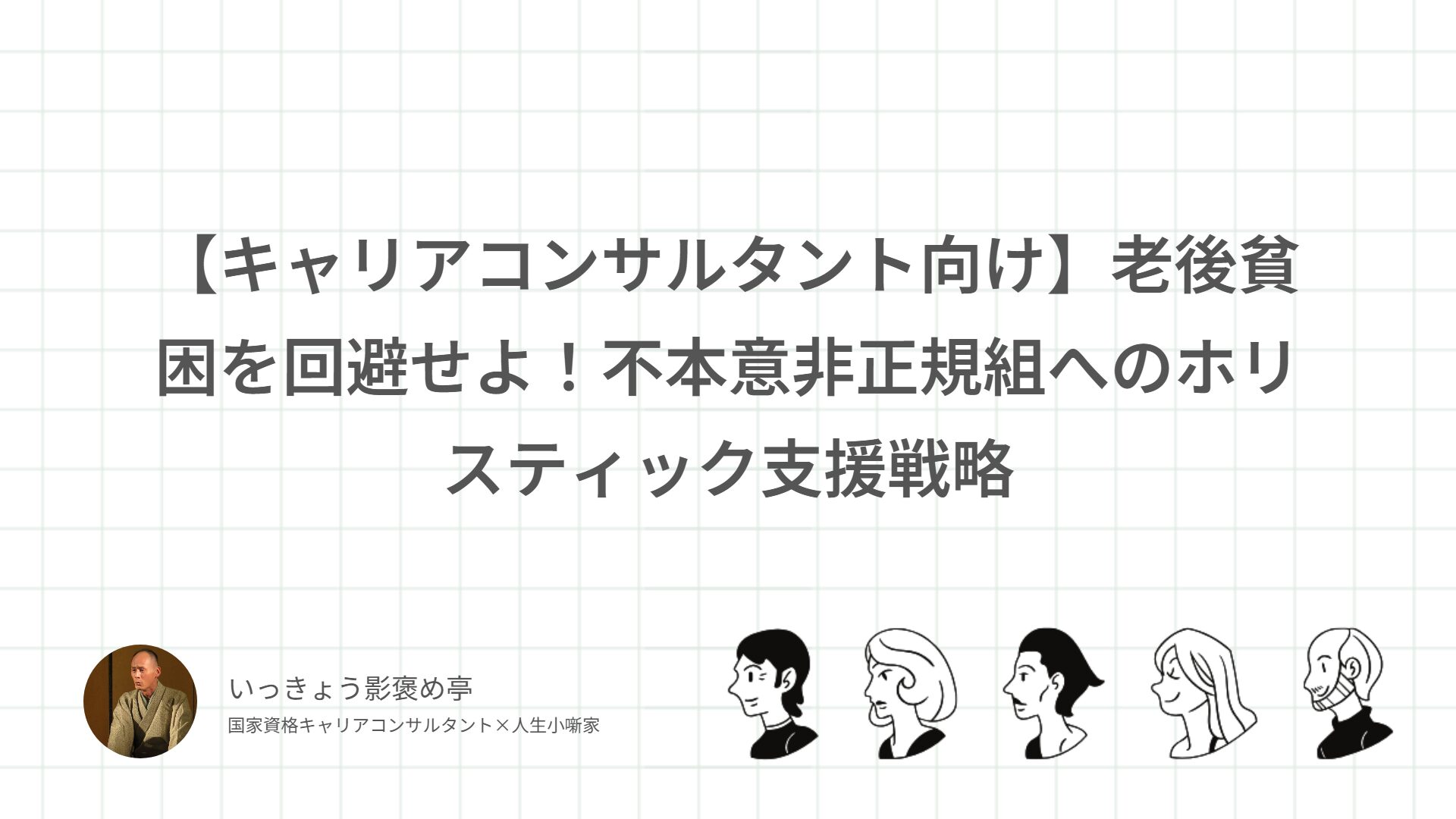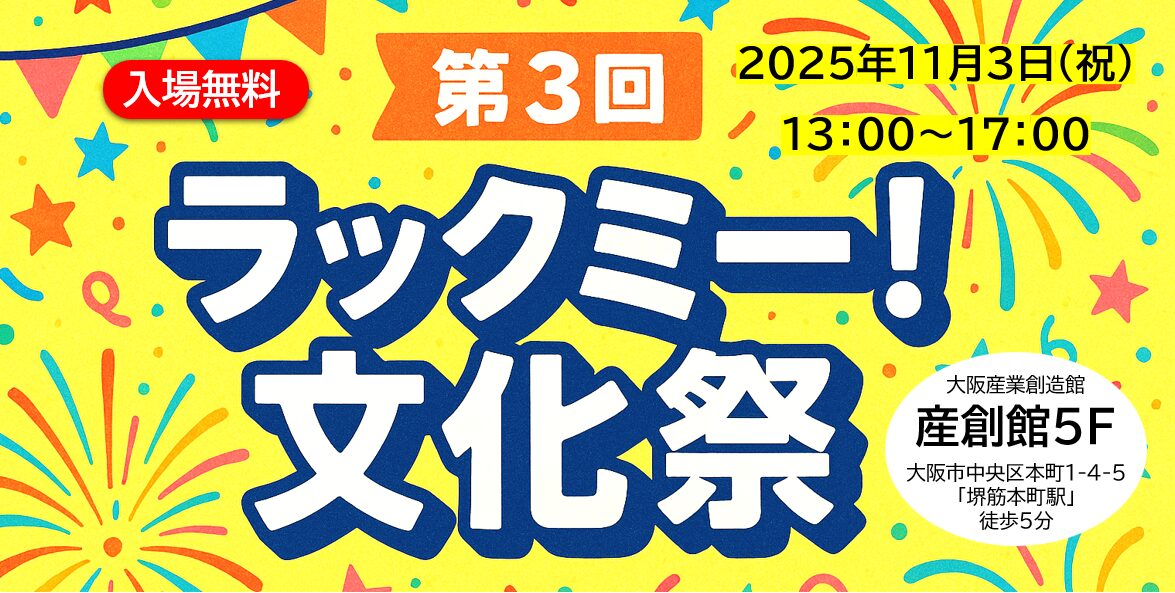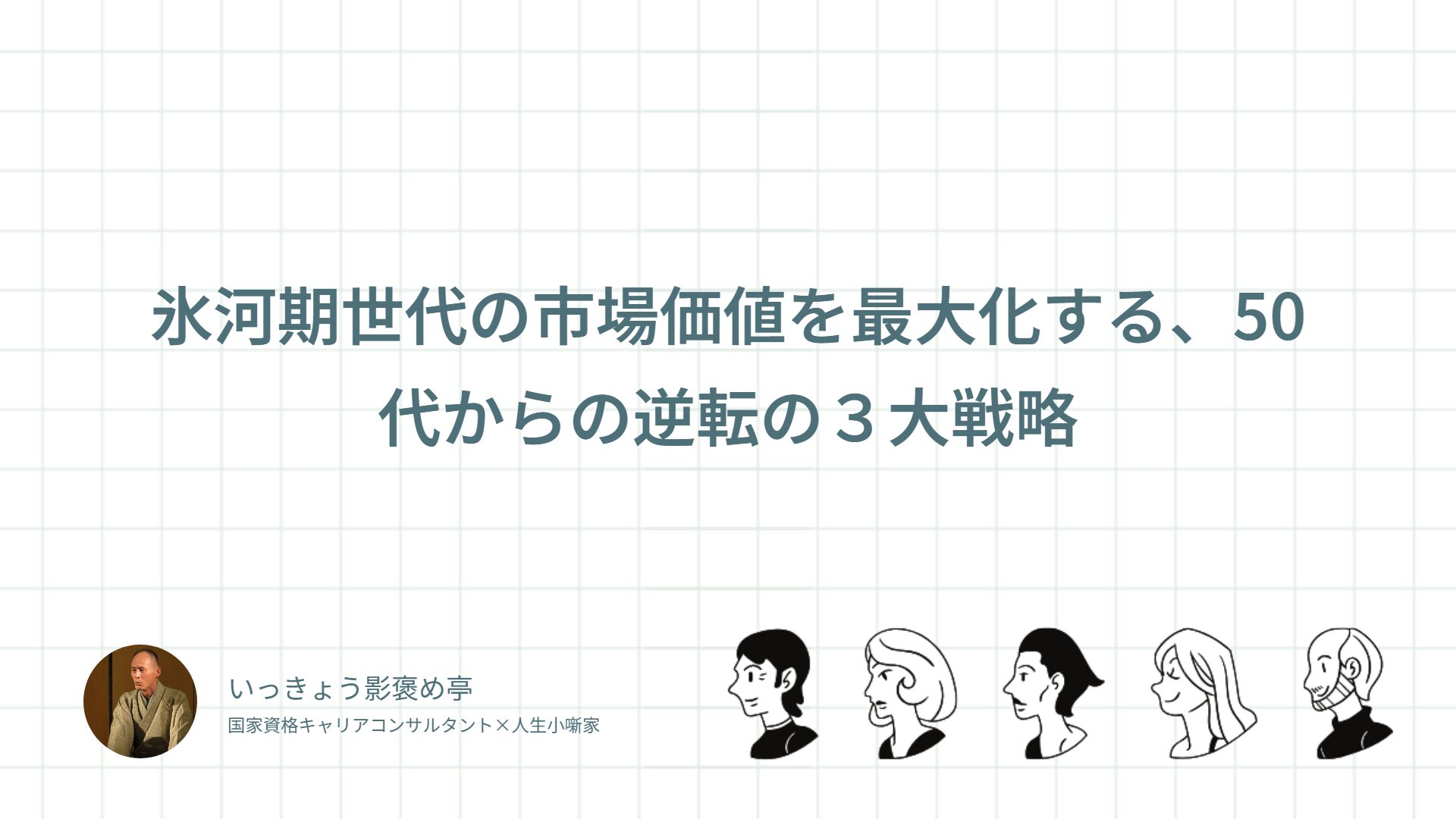なぜ今、バス業界にキャリアコンサルタントが必要なのか?~小噺:人手不足と就職氷河期世代の可能性~
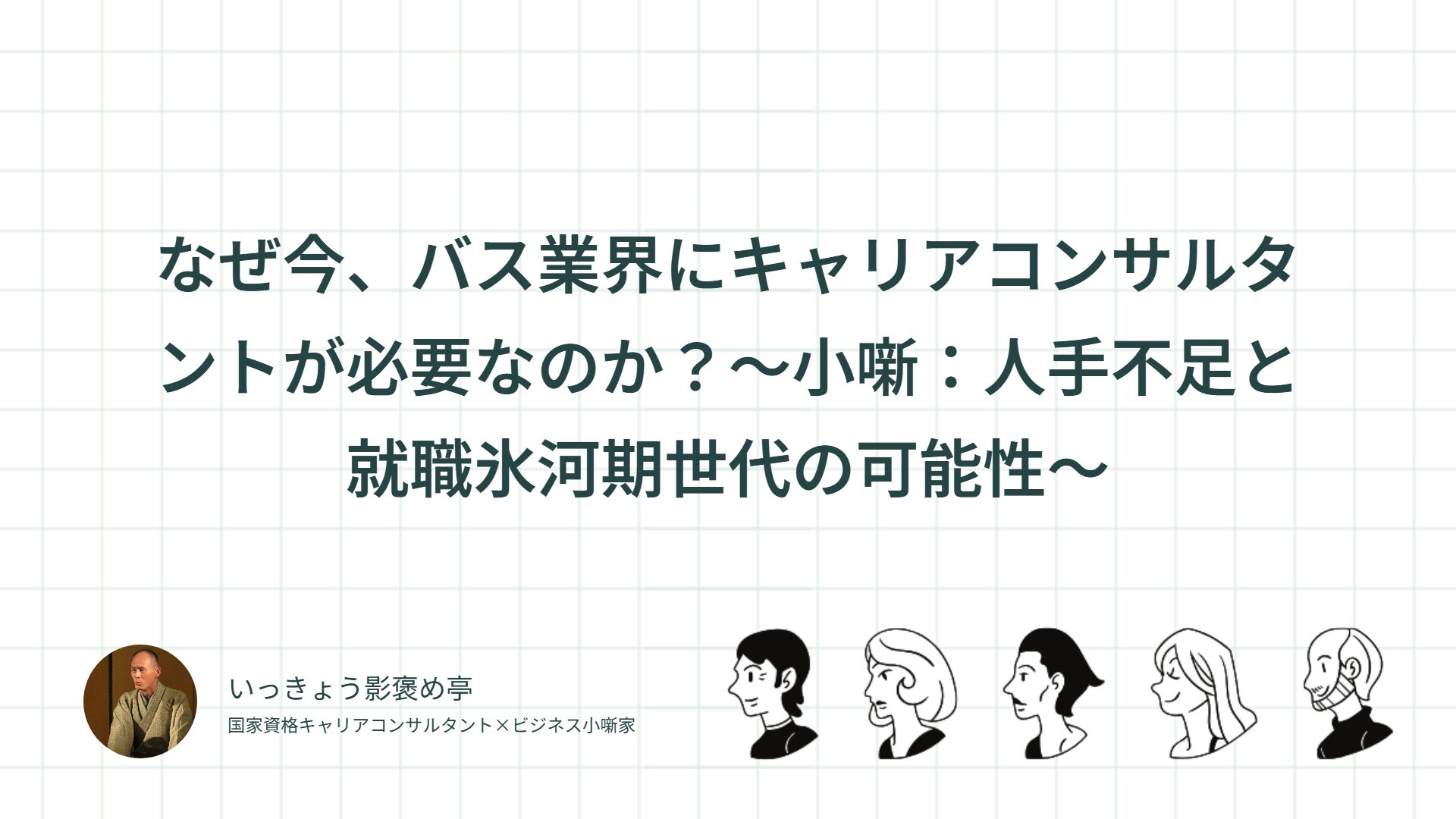
バスは、私たちの生活を支える大切な「足」です。しかし今、多くのバス会社が深刻な人手不足に直面しています。ベテランの引退、若者の敬遠により、地域交通の未来が揺らいでいるのです。
一方で、就職氷河期世代と呼ばれる人たちがいます。不安定な時代を生き抜き、豊かな社会経験と粘り強さを持つこの世代は、安定した仕事への意欲も強く、実はバス業界にぴったりの存在。しかし、まだ十分に活かされていません。
この両者をつなぐ鍵となるのが、「国家資格キャリアコンサルタント」です。個人の強みを引き出し、適職へと導く“戦略参謀”。彼らがいれば、バス業界に新たな人材の流れをつくることができるのです。
では、この3者が交わると、どんな未来が生まれるのでしょうか? そのヒントを、ある街角の噺から覗いてみましょう――。

小噺:人手不足と就職氷河期世代の可能性
この小噺は、「バス業界の人手不足」、「就職氷河期世代の活かされていない力」、そして「キャリアコンサルタントの専門性」という三つの課題と可能性をつなぐ“橋渡し”の視点から描いています。社会の隙間にある“もったいない”を、どう活かすか──そのヒントがここにあります。
序:導入(就職氷河期世代の悩み)
喜六
「清やん、最近ちょっと真剣に考えてることがあるんや」
清やん
「お、どないしたんや?」
喜六
「わいらの世代な、ずっと“就職氷河期”って言われてきたやろ?四十も過ぎて、なんや“何者でもない感”がすごいあるんやわ…」
清やん
「せやなあ。バブル崩壊の煽り受けた世代やもんな。でも、今からでも遅うはないで」
破:展開(バス事業者の悩みとキャリアコンサルタント)
とあるバス事業者の人事部長
「(深いため息)いやあ、清やん、喜六さん。もうこっちは悲鳴ですよ。運転手が足りんのです。昔は“地元の誇り”だったのに、今じゃ“きつい、休み少ない、客も厳しい”って、敬遠されまくりで…」
喜六
「バス会社も大変なんやなあ…」
清やん
「でも、部長はん。考えてみてくださいな。この喜六みたいな“就職氷河期世代”ってのが、実はバス業界にぴったりなんとちゃいますか」
人事部長
「なるほど、たしかに長く働いてくれる人材を探してるが…どうして彼らが向いてると?」
(蔵はん登場)
蔵はん
「ふむ、まさにそのとおりじゃな」
人事部長
「どちら様で?」
蔵はん
「わたしは“キャリアコンサルタント”。人と仕事をつなぐ“戦略参謀”とでも申しましょうか」
清やん
「先生、ええところにきてくれはった」
蔵はん
「うむ、氷河期世代は粘り強く、安定志向が強く、社会経験も豊富じゃ。さらに最近ではデジタルにも明るい人材が多い。そして何より、この世代は人口ボリュームが大きい。長期的に見れば、70歳までの雇用も視野に入れた持続可能な戦力となるのじゃ」
喜六
「……そんなふうに言われたの、初めてかもしれへんわ」
蔵はん
「戦さにおいて大事なのは“重心”といわれとる。バス業界の問題もまた、単に人手を集めるだけではなく、“誰を・どう活かすか”にある。就職氷河期世代のような、安定志向と経験のある人材こそ、バス業界が晒されている局面の“重心”になり得るのじゃ」
人事部長
「なるほど…でも、そういう人を見つけて、育てて、続けてもらうのは簡単じゃないですよ」
蔵はん
「そこにこそ、我らキャリアコンサルタントの出番がある。強みの棚卸し、心理的壁の越え方、リスキリングの支援。そして定着に向けたメンタルケアとキャリア設計…戦略的に“人材の戦力化”を支えるのですな」
喜六
「え?そんな支援があるんやったら…オレも挑戦してみたい気がしてきたで」
蔵はん
「喜六さん、君の経験と気持ちが“未来を支える橋”になるのですぞ」
急:収束(オチ)
人事部長
「まさか、自社の課題解決の鍵が“氷河期世代”と“キャリアコンサルタント”にあったとは…」
喜六
「そうと決まったら、オレ、大型Ⅱ種免許の勉強始めるわ!」
清やん
「ええなあ、喜六さん。今度こそ“何者か”になれる道を、自分で運転するんやなぁ」

音声版小噺:人手不足と就職氷河期世代の可能性
音声収録版があります。こちらで小噺が聴けます。
就職氷河期世代の“今”
「わいらの世代、よう我慢してここまできた思うで。でも、なんや自分の居場所が見つからへんのや…」

就職氷河期世代は、バブル崩壊後の厳しい雇用環境で社会に出た世代です。不本意な就職、非正規雇用、キャリアの断絶を経験し、現在40代後半~50代前半の中年期に差しかかっています。
この時期は、仕事の見直し、子育ての終盤、親の介護、自身の健康など、多くの課題が重なる“人生の曲がり角”でもあります。
その一方で、彼らは長年の社会経験、粘り強さ、そして近年では高いデジタルリテラシーにも長けているという、“掘り出し物”ともいえる特性を持っています。

バス業界の“課題”と“強み”
「バスはな、地域の命の流れや。そいつが滞ったら、街が弱ってしまうで」

バス業界は、深刻な人手不足と高齢化という二重苦に直面しています。運転手の仕事は長時間労働、カスタマーハラスメント(カスハラ)対応なども多く、若い人がなかなか定着しないという現実があります。
一方で、バス事業には“隠れた強み”もあります。例えば、長期雇用制度の整備(事業者によっては75歳まで)、大型運転という専門技術による安定した需要、そして乗客から「ありがとう」とお礼や感謝の言葉を直接受ける機会が多く、社会貢献をしているという実感できるという点です。
「参考資料」バス協調・共創プラットフォームひろしまより
さらに、事業者によってはフレキシブルな勤務体系を導入しているところもあり、親の介護や自身の体調変化に合わせて働き方を調整できる柔軟性も魅力です。こうした取り組みは、厚生労働省が推進する「治療と仕事の両立支援」の観点からも、今後ますます重要になると考えられます。

キャリアコンサルタントの可能性
「人を“つなぐ”仕事じゃ。戦で言えば、兵をどう動かすか考える参謀のようなもんじゃな」
こうした両者をつなぐ専門家こそ、キャリアコンサルタント。本人の強みや希望を丁寧に引き出し、必要に応じてリスキリングの支援を行い、「人材の戦力化」を図ります。さらに、採用後の定着支援にも深く関与し、職場での人間関係やストレス対応、長期雇用を見据えたキャリア設計にも関わります。
かつて厚生労働省が行っていた「バスジョブ!」のような取り組みは一時的なものでしたが、今後は国や自治体、バス事業者、そしてキャリアコンサルタントが連携して、持続可能な支援体制を築いていく必要があります。
そもそも厚生労働省がキャリアコンサルタントという国家資格制度を整備した背景には、「個人のキャリア形成を支え、生涯にわたる多様な働き方を実現する」ための社会基盤づくりという狙いがあります。これは高齢社会や地域活性化、働き方改革といった政策課題にも直結する重要な制度設計です。

最後に
「血が通わなかったら、人間もしんどいですな。地域も同じやと思います」
地域交通を担うバス事業者は、地域社会にとって血管のような存在です。人の流れという“血”が滞れば、社会の活力そのものが失われます。だからこそ、この“血管”を絶やさないためにこそ、氷河期世代の再チャレンジを支える出番なのです。
キャリアコンサルタントは、地域交通と就職氷河期世代という二つの課題の“架け橋”に立つ存在。まさに現代における「戦略参謀」として、社会に大きな価値をもたらす役割を担っているのです。
【お問い合わせ】
キャリアコンサルタントについてくわしく知りたい方は下記コメントからご連絡をお願いします。